

戦前日本の「聖地」巡礼の歴史を知る本が発売!新しい視点で探る観光の形
聖地巡礼の新たな歴史を探る
2025年5月26日、NHK出版から『戦前日本の「聖地」ツーリズムキリスト・日蓮・皇室』が発刊されます。本書は著者の平山昇氏が手掛けたもので、歴史的な視点から聖地巡礼の在り方を深く掘り下げています。
現代の聖地巡礼は、宗教はもちろん、漫画やアニメなどのご当地めぐりといった多様な形を持っていますが、昭和戦前期の聖地巡礼は、一味違った背景を持っていました。当時は、特定の思想に同調しない人々が排除されるという強い圧力が存在していたため、ただの旅行とは異なる意味を持っていました。
著者は、明治時代における社寺参拝が「迷信」とされていたことに注目し、日蓮とキリストを同一視する動きがどのように浸透していったのかを考察しています。明治神宮の創建が社会に与えた熱狂も、一般大衆に広がり、聖地巡礼が教養エリートから大衆へと普及していく過程を詳細に描写しています。
また、本書では「全国的な鉄道網の整備」がツーリズムの大衆化に果たした役割も明らかにしています。この時期、多くの人々が列車を利用して聖地に向かうことで、巡礼のスタイルが変化しました。本書を通して、昭和戦前期の聖地巡礼の社会的意義や文化的背景を理解することができます。
本書の目次は以下の通りです。
- - 序章: 聖地の日本化
- - 第一章: 日蓮と基督 ―― 高山樗牛と田中智学の日蓮像
- - 第二章: 教養主義と日蓮ツーリズム――身延山、富士身延鉄道、高山樗牛
- - 第三章: 天皇崇敬の「宗教」化 ―― 大逆事件と天皇の代替わり
- - 第四章: 明治神宮と渋沢栄一 ―― 意図せざる「聖地」の創出
- - 第五章: 体験と気分の共同体――大正期以降の伊勢神宮・明治神宮参拝ツーリズム
- - 第六章: 日蓮の「聖地」と明治神宮 ―― 田中智学による「聖地」の規範化
- - 第七章: 「聖地」のセット化(Ⅰ)――橿原神宮と「三大神宮」
- - 第八章: 「聖地」のセット化(Ⅱ)――田中智学の「五大聖地」巡拝
- - 第九章: 「聖地」のセット化(Ⅲ)――大軌グループと「三聖地」
- - 第一〇章: 総力戦体制と「聖地」ツーリズム――「自粛」下のツーリズムを正当化する論理
- - 終章: キリスト発、日蓮経由、皇室ゆき
著者の平山昇氏は、東京大学出身で、近現代史を専門とし、多くの著書や論文を執筆してきました。彼の研究を通じて、日本の聖地巡礼の歴史的背景を知る貴重な機会を提供してくれています。
この一冊を手に取ることで、戦前日本の聖地巡礼が持つ奥深い意味を知り、当時の社会状況や人々の意識について考え直す良いきっかけとなることでしょう。
書籍の詳細は以下のリンクから確認できます。
歴史を知ることは今を生きる私たちにとっても重要です。本書を通じて、聖地巡礼の本質に迫る楽しさを味わってみてはいかがでしょうか。




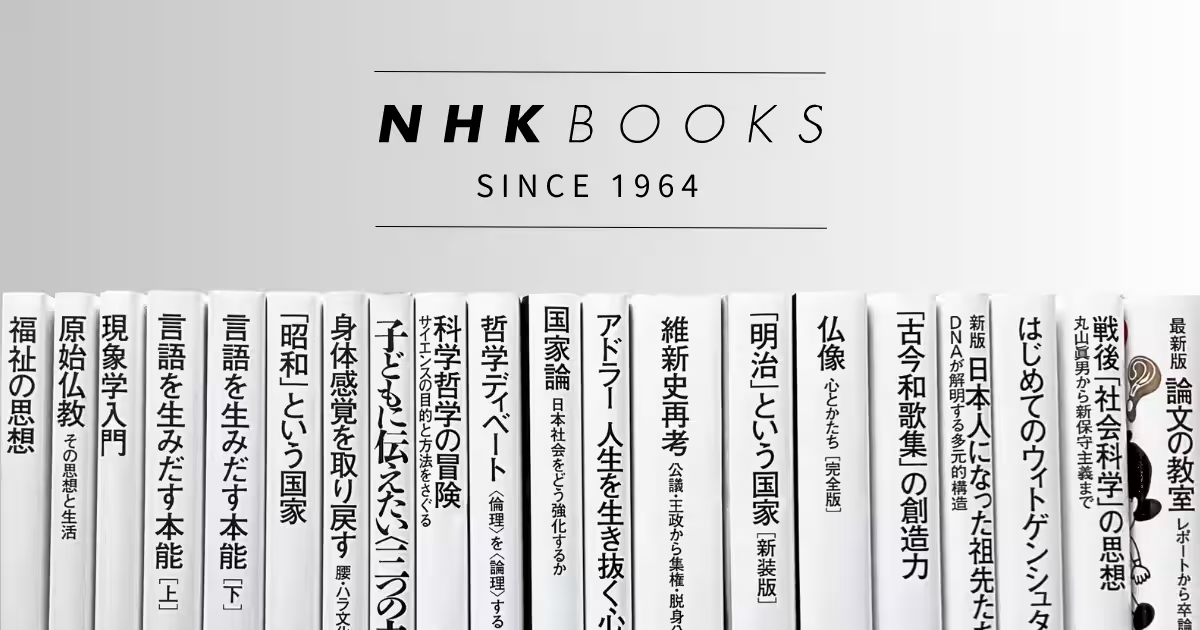
トピックス(その他)










【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。